













✓ 痛みを感じない人、痛くても体を動かせない人
✓ 麻痺などがあって自分で身体を動かせない人
✓ 体力が落ちて栄養状態の悪い人
✓ 意識がなくて自分で身体を動かせない人
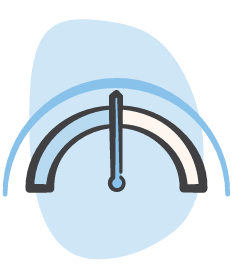
仰向けで寝ていると、仙骨部といわれるお尻の出っ張りの部分や尾てい骨、背骨、かかと、後頭部などにできることが多いです。
下半身麻痺で車椅子など長時間座っている姿勢の時には、坐骨と言われるお尻の部分にできることが多いです。
生まれつき足の感覚が鈍い人や糖尿病の合併症で足の感覚が鈍い人などは足にできることが多く、かかとやくるぶしにできることが多いです。

骨が出ている部分の皮膚が赤くなっていたりただれているのを見つけて褥瘡かな?と心配になった方は、かかりつけ医へ相談しましょう。
かかりつけ医のいらっしゃらない方は、褥瘡を専門として診察してくれる「形成外科」「皮膚科」の先生に相談しましょう。
訪問看護や訪問診療を利用している方はまずそちらに連絡しましょう。
予防・治療対策
✓ 毎日皮膚を観察することが大切です。
・圧迫やずれが原因でできてしまう傷ですので、それを避けるようにすることで予防ができます。
・オムツを使用していると排泄物などで皮膚が蒸れやすくなります。蒸れているとずれや摩擦を受けやすくなって皮膚が傷つく原因になるので、
・撥水性のクリームなどを塗って皮膚を保護することも大切です。
✓ 圧迫やずれが関連している場合
・自分で動けなくて寝返りが打てない時は、寝返りをするお手伝いをします。
・ふとんやベッドのマットレスが固い時は、やわらかい低反発のマットレスに交換することを検討します。
✓ 栄養状態が悪い場合
・栄養バランスの良い食事になるように気を付けたり、脱水にならないよう水分補給をしましょう。
褥瘡の局所治療
✓ 皮膚の一部が赤くなっている場合
・赤くなっている部分が悪くなっていかないか、皮膚の観察をします。
・摩擦やずれが加わって褥瘡が起きやすいような部位には、滑りの良いフィルムドレッシングを貼って保護することもあります。
・やせていて骨が出ているような場合は、皮膚を守るためにクッション性のあるパッドの絆創膏を貼って保護することもあります。
✓ 皮膚がただれたり、傷ができている場合
・医師が治療の判断をします。褥瘡を専門として診察してくれる「形成外科」「皮膚科」の先生に相談しましょう。
・お家で継続的に処置をするように指示があった場合には、指示のもと塗り薬・キズ薬を塗って保護したり、絆創膏を貼って保護します。
スミス・アンド・ネフューでは、様々な創傷ニーズに合わせた絆創膏を提供しています。
高機能な絆創膏は、病院などの医療機関でも使用されており、軽度の創傷から慢性創傷まで幅広い創傷に適しています。
高い通気性と吸収力、デリケートな方の皮膚を考慮した粘着剤など、高度な技術と素材を用いることで、傷の治り(創傷治癒過程)を妨げずに治癒を促します。
詳細については、以下の製品をクリックしてください。